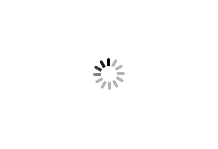高校生の頃、「このときのこの人物の心情を答えなさい」という形式の問題に解答するのが嫌でたまらなかった。
その理由は簡単で、「この人物」にもし「自分の名前」があてがわれ、見知らぬ誰かが自分の得点のために私にしかわかりえない気持ちをそれっぽく書くという状況を想定したとき、天邪鬼の私は間違いなく、どんな解答にも ――たとえ本文中で言及されていた内容が書かれていたとしても――「それは違う」と答えてしまうよな、と思ったからだ。
その一方で、誰かがものすごく切実な気持ちで、わずかな文章から、私のことを理解しようとして、共感してくれるとしたら、私は間違いなく、「わかってもらえて嬉しい」と思うだろう。
こんな風に、同じ文章で書かれたことであっても、書き手と読み手、そして描かれたものや人、あるいはそれらを取り巻く状況によって、全く違う意味を持つ。
書かれたら最後、読まれたら最後、人と人を否応無しに接続してしまう癖に、捉えどころのない「文章」に正解なんてものは当然なく、それでいて、この文章を書いている最中もこんな風に考えてしまう。
「書きたいことが正しく伝わるだろうか?」
小説かどうかを決めるのは、規範性ではなく人間の認識
文章を書き、読むという複雑怪奇な営みに対し、技術という方法でアプローチするのが公立はこだて未来大学のプロジェクト「きまぐれ人工知能プロジェクト作家ですのよ」だ。このプロジェクトの目的は、人工知能に小説を書かせる、というもの。

※画像はイメージです。
公立はこだて未来大学の松原仁教授を筆頭に2012年に始動したこのプロジェクトに朗報が舞い込んだのは、2016年のことだった。
理系的な発想を基盤にした短編小説を対象にした文学賞「星新一賞」の一次選考を突破したのだ。
「人工知能に小説を書かせる」という目的を目指し、開発者達は小説を作成するプロセスを「プロットの作成」と「文章の作成」の二段階に分けることでより自然な「小説」にたどり着いたという。
そうした中でプロジェクトチームの一員である名古屋大学の佐藤理史教授は講演の中で「小説」に対する以下のような見解を述べた。
要は、ある文章が小説であるかどうかを決めるのは、人間の認識の問題だと思います。何かテキストが満たすべき条件があるわけじゃなくて、受け手あるいは書き手がどう思うかという問題だと思います。
(佐藤理史 講演「“AI小説家”が星新一賞1次選考を通過開発者が語る『コンピュータが小説を書く日』」)
円城塔が描く近未来の文章のあり方
ある文章が小説であるかどうかを決めるのは、人間の認識の問題 ――こうした問題意識にもつながる「小説を書くということ」、そして「小説を読むこと」という行為の不確定さを描いたのが、円城塔の短編集『文字渦』に収録されている「梅枝」だ。
(※ 編注:次の画像より下に、結末を含めた内容の要約が続きます。要約を飛ばして読みたい方はこちらをクリックしてください)

※画像はイメージです。
今作では、技術が発達した近未来で、“ものをつくる人”として生きる「境部さん」と彼女が作った「もの」を中心に物語が進んでいく。
物語の世界では、生産コストの低下によって、「帋(し・かみ)」と称されるフレキシブルディスプレイが紙の上位互換として一般的に流通している。
さらに、帋で作られた本は「コンテンツを入れかえる」ことができ、さらに「文字の大きさやフォント、レイアウトを変更する」ことができる。
現実の本に比べはるかに柔軟性が高く、また携帯も簡単な帋の本を「境部さん」は「ただのデータだ」と一笑に付す。
なぜなら彼女はレイアウトやデザイン、文字のフォントまでが文意を変えると考えているからだ。
「レイアウトにより、デザインにより、文字の伝える意味内容は異なってくる。程度はあるが校訂作業だって必要だ。そういう意味ではこの本は」と和綴じの本を差し出してくる。題簽には『土佐日記』とある。「境部校訂本ということになる」
(円城塔 著「梅枝」『文字渦』)
そんな彼女は、旧時代的な「紙の本」を自ずから作成し、その過程を含めた行為が「本を読む」ことだと認識している。彼女が「本を読む」ために開発したのが、人工知能を搭載したロボットアーム「みのり」だ。「みのり」に与えられたのは、『国宝源氏物語絵巻』の「御法」を書き写すという作業。

※画像はイメージです。
「みのり」という機械の肝となるのが、「認識した画像に共感し書く」という行為ができることだ。つまり、認識した画像をその通りに書き写すのではなく、悲しい場面を書き写すときには、その悲しみを受けて涙を流して、震わせながら文字を書くというのだ。
そして、「境部さん」は、「御法」の筆写を足がかりとして、様々な書体で書かれた様々な文章の筆写が可能になるソフトウェアの開発を目指していた。
しかし、強い共感を伴いながら「御法」を書き写すことを繰り返す中、ある日「みのり」に異常が現れる。このロボットアームは、「御法」の筆写にのめり込むあまり、そこで利用された書体しか書けなくなってしまったのだ。
見る角度によって、創造性が宿る場所は変化する
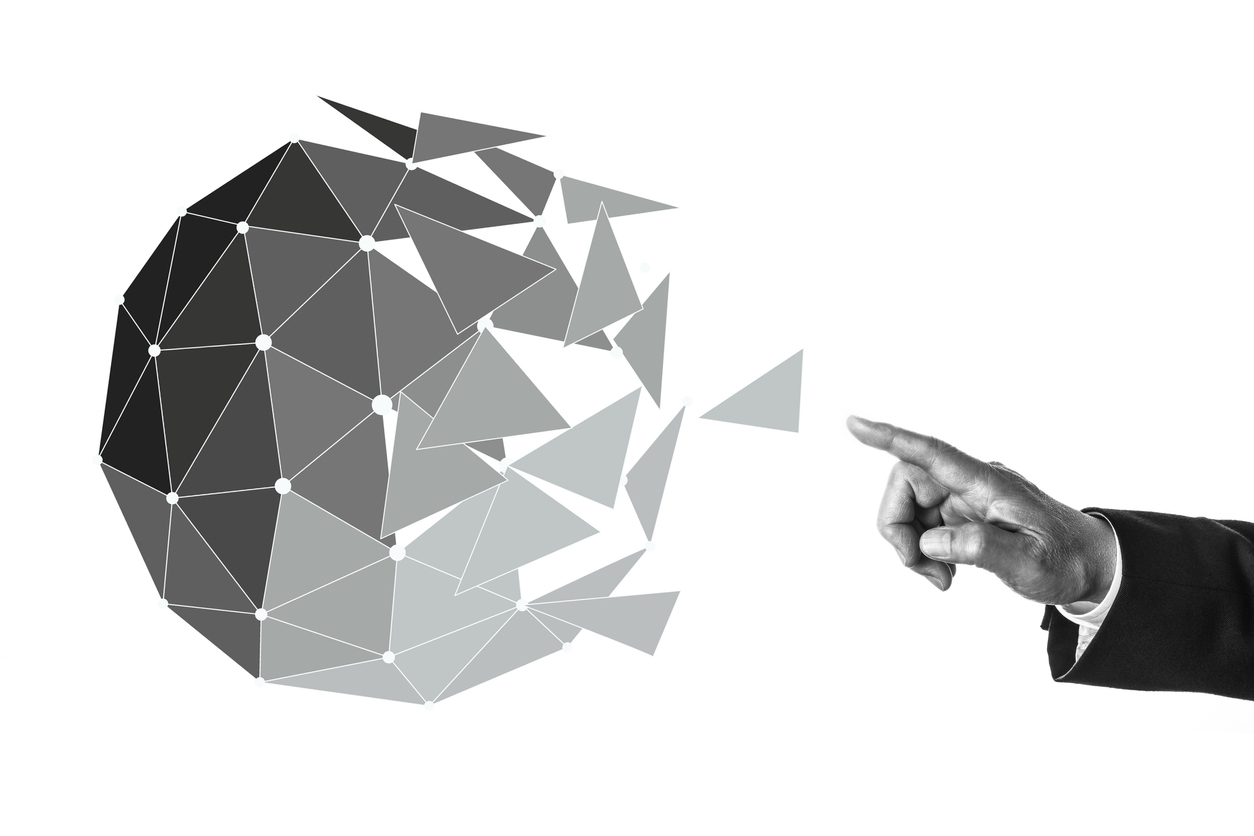
※画像はイメージです。
「みのり」が見せる一連の変容は、読者に「創意」というものの捉えどころのなさを突きつける。
例えば、「みのり」が応用可能な筆写を身につけたとして、その結果として出力される共感を滲ませた様々な書体を見た者は、そこにある表現の幅の広さに、創造性の豊かさを見出すかもしれない。
一方で、日々日々、同じ書体を書き続ける「みのり」は機械的な、創造性の欠如したもののように見える。
しかし、「みのり」が「御法」を書き続けることの根底に、作品に対する狂信があると知ったら、おそらくその評価はガラリと変わるに違いない。
なぜなら、人間の望みに対応し、様々な書体を書き続ける機械、よりも、「作品に対する思い」によって、同じ書体しか書けなくなった機械の方が「創造性がある」と感じられるからだ。
「文章を書くこと」、そして、「文章を読むこと」に含まれる創造性が、一体何によってもたらされるのか、その謎は、人類が文字を発明してから少なくとも5000年以上経った今なお、解明されていない。
しかし、 人工知能の開発を介し、「文章を書くこと」のプロセスを明らかにすることで、人間だけでは知りえなかった創造性に対する新たな認識が生まれるのかもしれない。