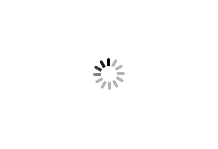あなたの家には、Amazonの「Dash Button」があるだろうか?
iedgeを読んでくれている読者のようなテックギークたちは、きっといくつか持っているだろうと予想しているが、ジャストシステムが2017年10月に行った調査によると「Amazon Dash Buttonを購入したことがある」のは5.7%、「知らない」と答えたのが33.7%とある。意外と浸透していないのだ。
一方で、同調査内のAmazon Dash Buttonを持っているユーザへの質問では「定期的に利用している」が63.0%、「ほとんど利用していない」「まったく利用していない」を除いた数値では88.9%となり、持っているユーザは積極的に利用している像も浮かび上がってくる。
そんなDash Buttonの販売を全世界で終了すると、2月28日にAmazonが発表した。(Dash Buttonを通じた注文は引き続き行える)
実は私はDash Buttonのヘヴィユーザなのだが、ここでぜひ、この製品が果たした役割を考え、次世代に何を残したのかを考えてみたい。
ホームIoTという「コンセプト」の理解を促した先駆者
Dash Buttonがいつ登場したのか覚えているだろうか。2014年である。意外と古い。
そのころはまだ、AIスピーカもなかったし、スマート電球やスマートプラグなんてもってのほか。まだ一般家庭には入ってきていない頃だった。
つまり「ホームIoT」というコンセプト自体がまだ、理解されていないところへ登場したのがDash Buttonだったわけだ。
当時のことはよく覚えている。私はすでにテック系の記事執筆や広告制作の仕事をしていたので、よく「IoTの記事を作ってください。Amazon Dash Button みたいな」とたのまれたものである。
モノのインターネットと訳されるIoTというコンセプトに、キュートな外観とシンプルな機能を備えて現実世界に登場し、多くの人にとって「IoT=Amazon Dash Button」という認識を植え付けたのだ。
その後のIoTを「コンセプト」から「製品カテゴリ」に押し上げた功労者
AIスピーカーが一般向けに発売されたのは、Amazon Dash Buttonの登場から1年後、2015年だ。
しかし、当時はまだAIスピーカーを「IoTガジェット」とは認識していない人が多かっただろう。AI搭載の喋るスピーカー。そんなものだったと思う。実際、それは事実だし、そもそもIoT=モノのインターネットというコンセプトの定義自体が曖昧なので仕方がない。
なぜIoTの定義は曖昧なのか。それは、モノのインターネットという言葉があまりに「当たり前」だからだ。パソコンだってスマホだって「モノ」なのだから、インターネットにつながればIoTと呼んでいいはずだ。しかし、実際にはそう呼ばない。人々がIoTという言葉を使う時は、そこに「意外性」というエッセンスが求められている。
なぜなら、IoTという言葉は明確に定義された技術用語ではなく、販売戦略上の自由度を含んだマーケティング用語だからだ。「こんなものがインターネットに接続されている」という意外性、そしてそこから生まれる利便性。これらを広くアピールするための広告コピーとして捉えるのが正しいだろう。

撮影:筆者
だからこそ、いまや世界最大のガジェット市場でもあるAmazonにとって、IoT関連の売り上げを確かなものにするためには手に取れるわかりやすさが必要だった。つまりそれが、Amazon Dash Buttonである。
ブランドロゴが書いてあるだけのシンプルな筐体であるにもかかわらず、ボタンを押すだけで注文が完了し、実際に翌日や翌々日には自宅に荷物が届く。意外性の面でも利便性の面でも申し分のない製品だ。
この存在がなければ、Philips Hueのようなスマート電球の魅力に人々が気がつくまでに、Philipsは多大な努力を要しただろう。Amazon Dash ButtonがIoTという言葉を、ただのコンセプトを表現するコピーから「製品カテゴリ」を示す言葉へ押し上げたからこそ、スマート電球はスムーズにその市場を広げたのだ。