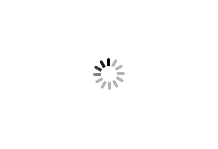最近、スマートフォンを買い換えた。
最低限のアプリしかないホーム画面にビクビクしながら帰宅して、パソコンからデータを同期した。 いくつかの項目にチェックをし、数分間待った末、同期の終了を確認する。
ホーム画面に使い慣れたウェブブラウザのアプリがあることを確認し、ほっと一息つく。試しに開いてみると、「位置情報を共有しますか?」というポップアップが出てきて、少し考えて、なんとなく「いいえ」を押した。
その日の夜、買い物の前にATMに行こうと思い立った。ウェブブラウザを開き、検索窓に使い慣れた銀行の名前を入力し、さらに半角空けて「atm」と入力した。
すると、銀行の公式ホームページと、ここから遠く離れた都心のATMの情報が並んだ。思いがけない文字の羅列に一瞬呆然とし、慌てて設定画面に移動し、位置情報をオンにした。
位置情報を共有したことで、膨大な情報の中から、まさに求められているであろう情報を AI が分析し、提示した。その結果として、5分後には、わたしは目的のATMで必要な金額をおろし終えていた。
「瑣末」な情報と引き換えに、日常的な利便性を獲得する。一見とても素晴らしい事のように思える。
だとすると、わたしの一瞬のためらいはいったいどこから生じたのだろう?
監視は脅威から誘惑へ変わる

※イメージ
本題に入る前にまず、ご紹介したい作品がある。それが、藤子・F・不二雄の短編作品『並平家の一日』だ。
あらすじはこうだ。
両親と姉と弟。標準世帯で暮らす並平家の生活は平凡だ。あまりに平凡すぎるくらいに。
そう、貯蓄額から勉強時間、夜ご飯の献立に至るまで、彼らの生活は統計から算出された消費者動向の平均にぴったりと一致するのだ。
そんな彼らの行動に目をつけた大手企業の会社員は、並平家を観察するために特別機関「メダカ機関」を立ち上げ、非凡なる「平凡な生活」を監視している。
さらにメダカ機関は企業と結託し、生活水準に影響が出ない範疇でマーケティングリサーチやシュミレーションを行うことで次なる流行を探り当てていく。
日常に監視の目を張り巡らすことで、消費者の動向を的確に把握し、その結果を即座に製品に反映させる。
『並平家の一日』が発表された1970年代には、フィクションの中でしかありえなかった世界が、今や当たり前になっている。
SNS で見た商品にいいねを押したり、様々なインターネットショップをめぐって商品を購入したり、あるいは一度カートに入れた商品を元に戻したり、私たちはインターネット上を徘徊することで様々な情報を提供している。
その「いいね」は、SNSがあなたに最適な情報を提示するヒントになる。あるいは、あなたが開いたページは、ABテストの真っ最中で何気なくクリックした「購入」ボタンはCVR(目標達成度)の上昇に貢献したかもしれない。
膨大な量の情報をAIが処理してくれるおかげで、わたしたちのちょっとした行動すらも、記録し、解析できるようになったのだ。
さらに最近では、IoT家電の普及により、洗濯機を回す時間や、電気をつける時間、はたまたお気に入りのテレビ番組までがデータ化され、インターネットで外の世界に接続されている。
些細な情報すら収集し、解析可能になった今、わたしたちの生活には、「監視」がついてまわる。
しかし、わたしたちと並平家の面々を明確に隔てるものが二つある。一つ目は監視に対する自覚。二つ目は監視されるものが情報化された自分の分身であることだ。
「監視に自覚的な人々」、もっと言えば「すすんで監視される人々」について言及したのが、社会学者であるジグムント・バウマンとデイヴィッド・ライアンだ。
彼らによる対話集『私たちが、すすんで監視し、監視される、この世界について リキッド・サーベイランスをめぐる7章』の中では、ヒトもカネもモノも仕事も流動的になった社会(リキッド・モダニティ)における「監視」に対する人々の認識についてこう指摘している。
監視され、見られているという条件は、脅威から誘惑に分類し直されているのです。可視性を高めるという約束、誰もが目にすることができて誰もが気づく「オープンな状態にある」という見通しは、最も熱烈に求められている社会的な承認の証拠であり、従って価値があり、「意義のある」存在である証拠ということになります。
ジグムント・バウマン+デイヴィッド・ライアン(伊藤茂 訳)『私たちが、すすんで監視し、監視される、この世界について リキッド・サーベイランスをめぐる7章』p 40
ものすごいスピードで情報が行き交う今、誰もが使いやすい形で情報を開示することは、社会的な信用や地位向上に直結している。
今の日本に「並平家」が現れたら、ひょっとするとトップインフルエンサーになるかもしれない。そう考えるとなんだか可笑しい。
しかし、明快で、便利な監視社会も、良いことばかりではない。
見られることで、消費されるわたしたち
わたしたちは、監視されるものとして、自分たちのコピーを“作り上げる”。
情報を操作し、自分の感情や行動を抑え込む。なぜなら、一度でも過ちが起きれば、価値は大暴落するから。
例えば、コカイン使用容疑で逮捕されたピエール瀧が所属する「電気グルーヴ」のCDや音源は、即時配信、出荷停止になった。
例えば、アルバイト従業員によって不適切動画が配信された大戸屋は、利益を下方修正し、従業員教育のために全店舗を一斉休業にした。
今や清く正しいことは、真っ当に情報社会に生きるための最低条件なのだ。
自分の価値を、常に無数の目が見張っている。さらに、自ら進んで他者に価値を提供する。人々が消費財であることが前提となった社会を、バウマンは「消費者社会」と呼んだ。
消費者社会の成員は自らも消費財であって、その成因は自らの消費財としての品質によって、消費者社会の真の成員になるのです。
販売可能な商品になること、そして商品のままでいることが、明確に表明されている場合は言うまでもなく、たとえ表明されず意識されることがなくても、消費者の関心ごとの中で最も強力な目標です。
消費財の魅力、すなわち消費行動を流す現在あるいは未来の欲望の対象の魅力は、消費者が自らの市場価値を高めようとする力によって評価されます。「自らを販売可能な商品にすることは」DIY 的な仕事であり、個人の義務です。次のことを明記しておきましょう。つまり、何かになるだけでなく、「自らを作り上げる」ことが課題であり、任務なのです。ジグムント・バウマン+デイヴィット・ライアン(伊藤茂 訳)『私たちが、すすんで監視し、監視される、この世界について リキッド・サーベイランスをめぐる7章』p 52
商品価値を提供するため、“清く正しい自分”を作り上げる中で、わたしたちには「不良品という烙印を押されること」への恐怖がつきまとうのだ。
違和感は、いつだって実用性に勝てない
はじめは気味悪かったけどね。考えててもしようがないからもらっちゃうことにしましたのよ。
藤子・F・不二雄「並平家の一日」『藤子・F・不二雄SF短編<PERFECT版>(5)メフィスト惨歌』
冒頭に戻ろう。ウェブブラウザアプリに位置情報の共有を求められたとき、わたしは、位置情報を共有することに対し、わずかばかりの気持ち悪さを感じ、ためらった。
しかし、一度その利便性を実感するとそのためらいは雲散霧消した。
『並平家の一日』の登場人物たちも、マーケティング・リサーチのために家に届く商品を不気味に思いながらも、あっさりと受け入れていた。
実用性を前にすると、わたしたちはちょっとした違和感や、不自然さを飲み込んでしまう。
だからこそ、その実用性や利便性の代償として何を提供しているのか、今一度考える必要があるのかもしれない。