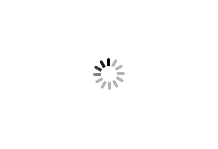私をはじめ、多くの人が使うようになった「IoT」という言葉。「Internet of Things」の略で、多くの場合「モノのインターネット」と訳されるが、いまいち、その全容がつかめない言葉だ。
このシリーズの初回では、IoTという言葉を最初に使った(とされる)ケビン・アシュトンが、実は「Internet For Things」と言っていたという話を紹介した。インターネットによる流通(=モノ)の管理についての言葉だ。
第2回では、「For」が「Of」に変わる過程で、その概念がどう変化したかを考えた。「モノのインターネット」という一般的な訳語よりも「インターネットのようなモノ」という言葉のほうが的確ではないかという意見を中心に述べている。
今回は、「IoT」という言葉を私たちの身近に浸透させた立役者について紹介しよう。
「IoT」という言葉を広めた立役者

日経新聞電子版で「IoT」を含む全記事を検索して時系列の昇順(古いもの順)に並べてみると、人事情報以外での初出は2011年8月30日となる。スマートグリッドについて語る村上憲郎氏(元・グーグル日本法人社長兼米本社副社長)のインタビューだ。
その後も2,3ヶ月に1度くらいは登場するが、そんなものである。ほぼ毎日IoT関連の記事が配信される現状とくらべて、もはや隔世の感すらある。
その中で、急に記事が増えはじめるのが2014年だ。IoTにとって大きな出来事のあった年なのだが、何だかわかるだろうか。実は、Amazonが dash buttonを発売したのが、この年にあたる。
この2014年は私にとっても印象的だ。ちょうど、会社員を辞めてフリーランスで執筆や編集の仕事を始めた頃である。なのでよく覚えているが、各所から「IoTをキーワードに取材してください。ほら、ダッシュボタンみたいな」と言われていたのだ。
今となれば「ダッシュボタンみたいなIoT」という言葉の奇妙さが目についてしまうが、当時の世の中はその程度の認識が普通だった。そういう意味でも、ここを起点として「IoT」という言葉の理解が深まったことがわかる。
次ページ >
dash buttonがIoTの立役者となれた背景
なぜdash buttonは「IoT」の立役者となれたか

当然ながら、それまでも今私たちが「IoT」と呼ぶような仕組みや製品は多くあった。しかしそれらは産業の現場を中心として活躍する「Internet For Things」たちだ。
ではなぜ、(それほど売れもしなかった)dash buttonが「IoT」という言葉を世に知らしめる立役者となれたのだろうか。
それは、まず「消費者が手に入れやすかったこと」「その恩恵がわかりやすかったこと」そして「見た目がかわいいこと」に尽きる。
dash buttonはひとつ500円で売られ、初回注文を500円引きにする仕組みで実質0円だった。押せば、本当にその翌日か翌々日には商品が届くし、製品ロゴを配したシンプルな筐体は実にかわいらしい。
そうして人々はそれを手に取り ――または、実際に買わずともAmazonのサイト上で何度となく目にすることになる。
それまで経済誌やネットニュースで目にしていた「あの新しいネット用語」が目の前に形となって現れているわけだ。そして、「ああ、これがIoTというものか」と頷いただろう。
こうして、「IoT」という言葉は広く浸透し、いま私たちが囲まれている、この現状 ――IoTという言葉が氾濫するに至った状況へと繋がっている。dash buttonがなければ、きっと数年は遅れていただろう。
dash buttonのもたらした「本当の価値」とは
次が最終回となるので、この連載記事で書いてきた内容をまとめよう。
まず、「IoT」という言葉を最初に使ったとされるケビン・アシュトンが実は「Internet For Things」という言葉を好んでいたという逸話を紹介し、流通や産業向けの技術として進化してきたことを書いた。
続いて、言葉が「Internet For Things」から「Internet Of Things」へと変わる過程で、そのコンセプトがどう変わっていったかについて論考してみた。
そして、それらを踏まえた上で私たちの身近に「IoT」という言葉を浸透させた立役者としてAmazonのdash buttonを紹介したのが本稿である。
最終回では、dash buttonがもたらした、本当の価値について触れよう。
前回の記事の最後に投げかけた「スマートフォンをなぜIoTガジェットと呼ばないのか?」という問いも、次の記事で明らかになる。
<最終回に続く>